|
2007年4月20日(金)〜5月2日(水)
(常設展) 4月6日(金)〜4月18日(水)
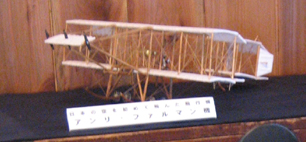
所沢は織物と飛行場の町でした。 明治から大正時代にかけ、
所沢は織物の集散地として繁盛し「所沢飛白」や「湖月縮」を生み出しました。
他方で、飛行場がつくられたことで、織物と飛行場の町として栄えることとなります。
4月5日は航空発祥記念日です。
日本で初めて飛行機が飛んだ日にちなみ、町場と飛行場の関係に着目し、所沢飛行場関連の模型や写真などを展示しました。
 |
 |
| 所沢の飛行場での飛行機の写真(喜多川さん撮影) |
飛行機の模型と飛行機関係の書籍 |
●所沢は日本の航空発祥の地
明治43年(1910年) 所沢に飛行場が建設されました。
明治44年(1911年)4月5日 徳川大尉が操縦するフランス製複葉機アンリ・ファルマン機が距離800m、1分20秒の飛行に成功しました。⇒ファルマン通りはここに由来します。
【飛行機新道(ファルマン交差点から北に下る道路)】
飛行機を所沢駅から運ぶためにつくられました
【木村・徳田両中尉の銅像】
日本最初の飛行機事故の殉職者の銅像(航空記念公園にあります)。所沢出身の歌人、三ヶ島葭子(みかじまよしこ)は、飛行場に関係する歌のほか、木村・徳田両中尉の殉難を弔う歌を詠んでいます。
【所沢飛行場駅】
現西武池袋線の所沢方面から秋津に400m程行ったところにありました。
【南倉庫(所沢航空参考館)】
西武の車両工場の跡地のところに、明治・大正・昭和初期に輸入された飛行機や国産の飛行機が格納されていました。
外国から飛行機による訪問者も多く、所沢の小学生達が国旗を持ち花束贈呈など、町をあげて歓迎したそうです。所沢は国際親善の町でもありました。 |
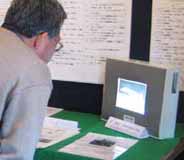 |
●大正天皇の行幸(大正元年)
所沢・川越付近で陸軍の特別大演習があり、北軍と南軍所沢市に分かれ、あわせて約10万人という大規模なものでした。
御幸町、元幸町(現元町)、寿町なのどの町名は、天皇の行幸をきっかけにつけられたものです。
また、大正天皇の行幸のほか、明治16年(1883年)の明治天皇の行幸もありました。
●戦後の町場と飛行場
所沢の飛行場は、戦後、米軍基地となりました。 |
【お話し会】
4月22日(日)午後2時より 「所沢飛行場物語 所沢の空を飛んだ飛行機達 」
講師 田中昭重氏(所沢航空資料調査する会・副会長 航空ジャーナリスト協会会員)
|
  |
4月29日(日)午後2時より 「所沢の町場と飛行場」
解説 松本 英男・三上 博史(井筒屋町造商店 ボランティアスタッフ)
|
  |
|
Copyright (c) 野老澤町造商店 All Rights Reserved.
|